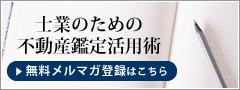士業専用ダイヤル
- ホーム
- 士業に役立つ不動産評価まめ知識
- 時事ネタ・トピックス
士業に役立つ不動産評価まめ知識
時事ネタ・トピックス 〜電通グループ、本社ビル売却〜
2021/06/306/29の日経新聞に
「電通グループ、本社ビル売却益890億円」
という記事が掲載されていました。
「東京・汐留の「電通本社ビル」の売却の検討に入った」
「営業損益で約870億円、
最終損益で約590億円の押し上げ要因になる」
「売却後も11年間の賃貸借契約を結び、
ビルの大部分は電通グループが使い続ける予定」
とのことです。
【セールアンドリースバック】
自社ビル等の不動産や機械設備等を売却し、
その買手から当該物件のリースを受ける取引です。
■キャッシュフローや資本効率の向上
借り入れをせずに手元資金を確保でき、
バランスシートのスリム化等も期待できます。
■物件の継続使用・事業の継続が可能
売却とリースバックの契約を同時に結ぶため、
そのままこれまでとおり物件の継続使用ができます。
■売却損益の計上
売却損益が出ますので、決算に大きな影響があります。
中小企業の場合でも、
セールアンドリースバックは普通に検討され、
売却損益の計上で決算(税額)が大きく変わることが
インパクトとして受け止められることが多いです。
また、売却先の選定や賃料の設定如何で、
事業承継・相続対策として活用されるケースも見られます。
【鑑定士的な視点から】
簿 価 譲渡益 売買価格
1,790億円 + 890億円 = 2,680億円
別の記事でも、
「東証1部2部上場企業の不動産売却調査では、
2001年以降、売却額で国内最大規模」
と記載されていて、
どのように価格決定されたのか非常に興味深いです。
不動産鑑定士は、適正な売却価格の評価、
リースバックの適正賃料の評価を行います。
どんな資料や利回りに基づいて評価したのか、
見られるものなら見てみたいと思います。
【個人の住宅でも】
似たような仕組みとして
「リバースモーゲージ」があります。
自宅に住み続けながら、
その自宅を担保に老後資金を借りることができる
というものです。
リバースモーゲージの担保評価も
不動産鑑定士が関与することがあります。
時事ネタ・トピックス 〜中小M&A仲介にルール〜
2021/06/296/28の日経新聞に
「中小M&A仲介にルール
登録制や自主規制で悪質業者排除」
という記事が掲載されていました。
「後継者不足などで企業再編の需要が高まるが、
悪質な仲介業者によるトラブルも目立つ。」
「提示された買い取り価格は訪問のたびに上がり、
いつの間にか当初の3倍になったが、逆に不信感が募った。
「価格の算出方法などわからないことだらけ。
買い手のことしか考えていないようにみえた」。」
【不動産評価の現状】
一般的には会計士さんや税理士さん等がメインとなり、
会計・税務・財務面の検討は
詳細に行われていることが多いですが、
不動産の評価まで詳細に行われていることは少ないです。
■固定資産評価額を活用するケース
・土地建物とも、評価額そのままを採用。
・土地は0.7で割り戻し、建物はそのまま。
■相続税評価額を活用するケース
・土地は、財産評価基本通達に基づき評価(8割評価)。
・建物は、通達に従い、固定資産評価額を採用。
【不動産評価の問題点】
固定資産評価額や相続税評価額には、
以下のような問題点があります。
不動産がほとんどない会社や、
あったとしてもわずかな場合は影響も軽微ですが、
不動産取引を目的とするM&A(不動産M&A)や
社歴が古く不動産を多数所有する会社などでは
M&A価格に大きく影響してしまうことがあります。
・土地を時価水準に割り戻ししていない。
固定資産評価額は7割、相続税評価額は8割水準です。
・都市部の土地は、実勢価格より安く、割安傾向。
・地方の農家集落地等は、実勢価格より高く、割高傾向。
・建物は、新築時ほど割安で、古くなるほど割高になっている。
・大規模修繕の有無や維持管理の良否が全く反映されていない。
・収益物件であっても、賃貸収入の多寡が全く反映されていない。
・土地建物それぞれに算出しているだけで、
複合不動産として一体的な目線での検討が行われていない。
このような問題点を洗い出して精査してみると、
不動産の評価が倍半分以上変わることも
決して珍しくありません。
【まとめ】
相互の信頼関係を構築するためには、
適切な評価を行うことが大切です。
M&A(株価)であっても、
なぜその価格になっているのか。
しっかり前提条件と算定内訳を見ていくことが重要です。
時事ネタ・トピックス 〜土砂崩れ、市街地に危険〜
2021/06/256/23の日経新聞1面に
「土砂崩れ、市街地に危険」
という記事が掲載されていました。
全国の「市街地にある住宅92万戸が
土砂災害を警戒すべき区域に建っている」
「日本は近年、気候変動の影響で
頻繁に豪雨に見舞われて」いる。
「土砂災害警戒区域に指定されても、
新たな開発への規制はない。
危険度の高い「特別警戒区域」でも、
安全対策などの規制をクリアすれば
開発は許可されてきた。」
「北九州市は土砂災害の
恐れがある斜面の住宅地について、
現状は市街化区域であっても、
住宅建設を規制する「市街化調整区域」へと
見直す方針を打ち出した。」
【土砂災害(特別)警戒区域】
■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
評価における減価率は、±0〜▲10%が中心です。
固定資産評価でも±0〜▲10%までが大半ではないでしょうか。
一方、国税の通達では、減額補正はありません。
土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価では、
「宅地としての利用は法的に制限されない」
「土地価格の水準に既に織り込まれている」
との理由が記載されています。
仮に、土地価格の水準に
織り込まれていない場合はどうなるのか。
路線価図だけでは織り込み有無の判断は難しいですが、
適用の余地はわずかながら残るのかもしれません。
現実の取引であれば、
イエローゾーンであっても、
指定の有無は一定の影響があると思われます。
■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
評価における減価率は、▲30%程度が中心です。
固定資産評価では、敷地の一部でも
レッドゾーンに指定されていたら、
敷地全体について減価を適用するところが多いです。
国税の通達では、面積割合に応じて▲10%〜▲30%。
がけ地補正率も乗じた最大で▲50%です。
開発指導要綱等で
現実的には開発不可の場合も多く、
そもそも宅地の価格から減価をするのではなく、
実質的に市街地山林と同視できる場合もあります。
【区域の指定】
以前は指定されていなくても、
指定区域はどんどん増えていっていますので、
現在は指定されている可能性もあります。
また、現在指定されていなくても、
指定には地元との協議など時間がかかるので、
実質的にはイエローないしレッドゾーンに
該当する場合もありますので注意が必要です。
物件調査の際に、周辺に山や傾斜地があれば、
まずは土砂災害(特別)警戒区域の指定の有無を
調べることが大切です。
「○○市 土砂災害」と検索すれば、
ネットでも簡単に調べることができます。
(最新の指定状況ではないこともあります)
時事ネタ・トピックス 〜京都・ホテル開業ラッシュ〜
2021/06/226/11の京都新聞に
「観光客激減の京都、でもホテル開業ラッシュ
ワクチン進み攻めの投資」
という記事が掲載されていました。
「新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、
京都市内でホテルの新規開業が相次いでいる。
インバウンド(訪日外国人客)は激減して、
開店休業状態のホテルも多いが、
ワクチン接種が着実に進む状況を受け、
秋以降に観光需要が一定回復するとの見方が台頭。」
「各ホテルはコロナ後をにらみ、
国内観光需要の取り込み準備に余念が無い。」
とのことです。
【地価LOOKレポート(国土交通省)】
令和3年第1四半期(R3.1.1〜R3.4.1)の
京都の商業地については、
■京都駅周辺
新型コロナウイルス感染症収束後を見据えた
新規開設需要も見られるものの、
投資家等は今後の開発動向を視野に入れつつ
不動産市況を冷静に見ている。
■河原町
感染拡大収束後を見据えた
出店計画、収益ビルの取得需要も散見される。
■烏 丸
感染拡大収束後を見据えた店舗の出店や
オフィスの拠点設置等の動きが継続している。
【国内需要の取り込み】
地価LOOKによると、京都の商業地では
新型コロナウイルス感染症収束後を見据えた動きが
随所に出てきています。
京都のホテルについても、
これまでのようなインバウンド需要のみではなく、
まずは国内需要を取り込み、
将来的なインバウンド需要の回復を
期待する流れが基本となっているようです。
【伏見稲荷大社】
京都でインバウンド需要が強かった場所といえば
伏見稲荷大社が挙がるのではないでしょうか。
「外国人に人気の観光スポットランキング」等で
日本で最も訪日外国人に人気の観光地となっていました。
ホテルは攻めの姿勢(国内需要の取り込み)で
市内中心部の商業地の地価は横ばい傾向ですが、
インバウンド需要が特に強かった
伏見稲荷大社などの地域では、
引き続き需要が弱い状態が続くものと予想されます。
時事ネタ・トピックス 〜以前からの土地賃貸借契約〜
2021/06/096/7の朝日新聞で、
「関電、元助役側から高値で土地を賃借」
という記事が掲載されていました。
「資機材置き場として
高値で借りていたことが分かった。
関係会社側が得る収入は相場の2倍超だった。
関電関係者によると、
社内で賃料の高さが指摘され、
関電はこの賃貸借契約を今年3月に解除した。」
とのことです。
関電に対して何か言いたいのではなく、
昔からの土地賃貸借契約についてのみ取り上げます。
【問題の所在】
昔からの土地賃貸借契約については、
改めて賃料をチェックした結果、
現在では適正とはいえない内容に
なっている場合があります。
今後どのように見直していけばよいのか。
しっかり検討していく必要があります。
■契約当初は適正だったが、現在は不適正
契約当初は適正な地代となっていても、
その後の経済情勢の変動により、
割高・割安な地代となっていることがあります。
適正な範囲(幅)の間であればよいのですが、
著しく割高・割安の場合は見直しが必要です。
地代が割高・割安であることは、
当該土地価格(底地・借地権価格)に大きな影響があるほか、
地代支払いというキャッシュフローにも影響し、
最悪の場合は寄付や利益供与と言われるリスクも。
■契約当初から適正ではなく、現在も不適正
契約当初から、なんらかの事情や意図で
割高・割安に地代が設定されているケースです。
本来は他の理由での金銭授受なのに、
土地賃貸借契約に含めてしまっていることがあります。
地代の定め方は下記のとおりですが、一般的には
適正な範囲を超えた土地価格or利回り
に基づいて地代が決まっています。
今回の関電のケースは、新聞報道によると
こちらの可能性があるということです。
(詳細の内容については不明です。)
【賃料の定め方】
地代の賃貸事例は、売買事例と違って
収集するのが難しく、そもそもの件数も少ないです。
そのため、新規地代の定め方としては、
鑑定評価における積算法を適用することが多いです。
土地価格 × 利回り + 公租公課 = 地代
土地価格 × 利回り(粗利回り) = 地代
とてもシンプルな計算式です。
土地価格も利回りも適正な範囲であれば、
求められる地代も適正な範囲となります。
問題が生じているケースは、
土地価格or利回りが、著しく高いor低い。
ここに集約されます。
(一時金を多額or少額にするケースもあります。)
【まとめ】
以前からの土地賃貸借契約について、
現時点で見ても適正な内容となっているか。
数年に一度はチェックすることをオススメします。
士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

- 不動産評価によるメリットがどれくらいあるか知りたい
- クライアントにどのような戦略的な提案ができるか知りたい
- 相手方が出してきた不動産評価の内容や意図が知りたい
などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!
TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)
※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。
※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会